The post 上司に送る年末の挨拶メールの例文とマナーを解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
年末は、一年を振り返り感謝の気持ちを伝える絶好のタイミングです。特に、上司に対して年末の挨拶メールを送ることは、単なるマナーではなく、キャリア形成においても重要な役割を果たします。
この記事では、上司に送る年末挨拶メールの作成方法・例文・注意点を解説します。
上司への年末の挨拶メールが必要である理由

年末の挨拶は、直接対面で行うべきです。しかし、相手が出張に出ていたり、拠点の場所が異なるなど、話ができないこともあるでしょう。そのような場合は、メールで連絡をするのが望ましいでしょう。
年末挨拶メールは、上司との関係を深め、来年に向けた良好なコミュニケーションの基盤を築くためのものです。メールでの挨拶を怠ると、感謝の気持ちが伝わらず、上司から「礼儀が足りない」と評価される可能性もあります。
キャリアを考える上で、上司への感謝をしっかり表現することは、信頼関係の強化につながり、将来的な昇進や評価にも好影響を与えるでしょう。
関連記事
上司に送る年末の挨拶メールのタイミングと送信時の注意点

年末の挨拶メールを送る適切なタイミングとは
年末挨拶メールは、できるだけ年内に送ることが基本です。
多くの企業では、年末は業務が立て込む時期のため、12月25日から28日あたりが理想的な送信日となります。相手の休暇が始まる前に送ることで、確実に読んでもらえる可能性が高まります。
年末の挨拶メールにおける注意点
返信を期待しない
年末の忙しい時期に返信を強制しないようにしましょう。「返信は不要です」と添えたくなるかもしれませんが、返信するかどうかは相手が決めるものです。
相手との距離感を考える
相手と心理的な距離がある場合は、個人的な話題は避け、業務の成果や感謝の言葉を中心に構成することが望ましいです。相手との距離が近い場合は、休暇の過ごし方など少し個人の話を入れても良いでしょう。
件名はシンプルにする
件名は30文字程度で簡潔にします。例:「年末のご挨拶」
関連記事
上司に送る年末の挨拶メールに含めるべき内容

年末の挨拶メールには、次の要素を盛り込むと効果的です。
| 挨拶 | シンプルに「今年1年お世話になりました」から始めます。 |
|---|---|
| 感謝の言葉 | 具体的なエピソードや支援に対する感謝を伝えます。 |
| 来年の抱負 | 来年の目標や期待を述べ、前向きな姿勢を示します。 |
| 結びの言葉 | 良いお年をお迎えくださいという一言で締めくくります。 |
関連記事
フォーマルなトーンと適切な言葉選びの重要性について

上司に送るメールでは、フォーマルなトーンを保つことが大切です。ビジネスメールでは、丁寧な敬語を使い、失礼にならない表現を選ぶことが重要です。
特に年末の挨拶メールは日頃の感謝を伝える場面なので、感情に流されず、冷静かつ丁寧な文体でまとめましょう。
年末の挨拶メールの書き出しと結びのフレーズ(例文)
書き出しのフレーズ例
- 今年1年間、大変お世話になりました。
- 年末のご挨拶を申し上げます。お忙しいところ恐縮ですが、一言お礼を伝えたく、メールをお送りいたします。
関連記事
- ビジネスメール「使えるフレーズ集」冒頭の挨拶・書き出し
結びのフレーズ例
- どうぞ良いお年をお迎えください。
- 来年も引き続きご指導のほど、よろしくお願いいたします。
関連記事
上司との関係性別・年末の挨拶メールの例文

年末の挨拶メールでは上司との関係性に応じて、メールのトーンや内容を調整する必要があります。
直属の上司へ送る年末の挨拶メール例
年末のご挨拶とお礼
山田部長
お疲れ様です。平野です。
今年1年間、大変お世話になりました。
おかげさまで、大きなプロジェクトも無事に完了することができました。
これもひとえに山田部長のご指導とサポートのおかげです。
来年も引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。
平野友朗
部門長や社長へ送る年末の挨拶メール例
年末のご挨拶
山田社長
お疲れ様です。平野です。
今年もご指導いただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、業績目標を達成することができました。
これも社長のビジョンとリーダーシップのおかげと感謝しております。
来年もより一層精進してまいりますので、
引き続きご指導のほどお願いいたします。
どうぞ素晴らしい新年をお迎えください。
平野友朗
上司に送る年末の挨拶メールで避けるべき表現

年末挨拶メールで避けるべき表現をまとめました。
| カジュアルすぎる言葉 | 「今年もお疲れ様でした!」は避けましょう。 |
|---|---|
| 長すぎる自己アピール | 簡潔に感謝を伝えることが重要です。 |
| 返信を求める表現 | 「ご返信いただければ幸いです」は控えましょう。 |
来年に向けたポジティブなメッセージも伝えましょう

年末の挨拶メールには、来年に向けたポジティブなメッセージを含めることで、上司に好印象を与えることができます。来年の目標や改善点を一言添えると、前向きな姿勢が伝わります。
来年に向けたポジティブなメッセージ例
- 来年はさらにチームに貢献できるよう、業務改善に努めたいと思います。
- 来年も新たな挑戦を通じて、成長していきたいと考えております。
まとめ
年末の挨拶メールは、上司に対する敬意と感謝を伝える大切なタイミングです。返信は求めずに、感謝の気持ちを言語化し、適切なタイミングで届けるようにしましょう。短く簡潔に、かつ丁寧にメールをまとめることで、上司との信頼関係を深めることができます。ぜひ、この記事を参考に、年末の挨拶メールを作成してみてください。
The post 上司に送る年末の挨拶メールの例文とマナーを解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post お客様へ送る年末の挨拶メールの書き方と例文集 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
はじめに
年末はお客様に感謝の気持ちを伝える絶好の機会です。メールでの年末の挨拶は、顧客関係を強化し、次の年度に向けて信頼を構築する大切な一歩です。
年末の忙しい時期でも、しっかりと気持ちが伝わるメールを送ることで、お客様との良好な関係を維持し、新たなビジネスチャンスを生む可能性も高まります。
本コラムでは、年末挨拶メールの重要性やタイミング、内容、トーン、注意すべきポイントを解説し、関係性に応じた例文やフレーズ集も紹介します。ぜひ活用してください。
お客様への年末挨拶メールが重要である理由

年末は一年の締めくくりとして、今までの感謝を伝える最適な時期です。全く連絡が取れていなかったお客さまにメールを送ることで思い出してもらえる可能性もあります。
お客様に感謝の気持ちを伝えることで、顧客との信頼関係を深め、翌年のビジネスにも良い影響を与えます。
ビジネスメールでお客様への年末の挨拶がもたらすメリット

お客様との信頼関係の構築
定期的に接点を作ることは、ビジネスにおける信頼関係を築く基本です。
本来であれば、定期的に電話をする、メールを送るなどができたらいいのですが、それが難しい場合でも年末年始などのタイミングでメールを送るのが節目としても分かりやすいでしょう。
お客様へ感謝を伝えることで印象アップ
今年1年の感謝の気持ちを伝えることで、企業や担当者としての好感度が上がり、翌年のやり取りがスムーズに進む可能性が高まります。
関連記事
お客様へ年末の挨拶メールを送る適切なタイミング

年末の挨拶メールは、適切なタイミングが重要です。年内にお客様が読むことが望ましいため、以下の点に注意しましょう。
送信日は年内に設定する
多くの企業で年末年始に長期休暇を設けています。年末休暇に入る前の最終出社日に送るのが一般的です。
休暇のタイミングはお客さまに教えていただくか、ウェブサイトなどで確認をしましょう。相手の最終出社日が分かる場合、その日の午前中や前日がベストタイミングと言えます。分からない場合は、12月25日あたりに送ると良いでしょう。
タイミングが早すぎないように注意する
仮に12月20日頃に送ったとします。すると、そのメールに対しての返信が発生し、相談や依頼が生まれるかもしれません。
挨拶後に新たな仕事のやり取りが発生しない方がいいならば、あまり早い時期に送らないようにしましょう。
お客様へ送る年末の挨拶メールに含めるべき内容
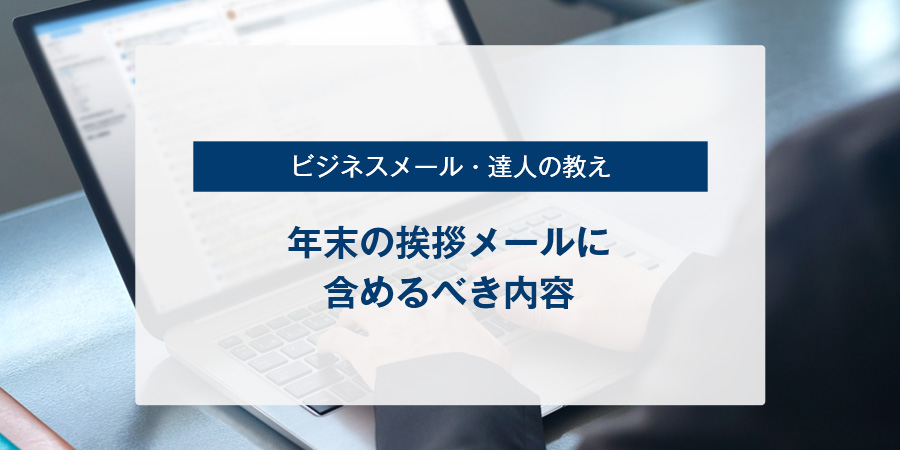
年末の挨拶メールには、以下の要素を含めると効果的です。
挨拶
年末のご挨拶として、「今年1年ありがとうございます」「今年は大変お世話になりました」といった形式が一般的です。
感謝の言葉
今年のサポートやお取引に感謝する言葉を忘れずに。そのまま感謝の気持ちだけを書くとテンプレートのようになってしまうので避けたいところ。
どんな仕事があったのか、どんな成果があったのか、そこでどう感じたのか……相手がありありと思い出せるように具体的に書くとよいでしょう。
来年の期待や意気込み
今年の振り返りだけでなく「来年も引き続きよろしくお願いいたします」のように来年についても触れます。
具体的にどのような取り組みをするのか、関わりをするのかなどを書くとよいでしょう。
お客様へ送る年末挨拶メール向け・書き出しのフレーズ集

カジュアル(一般的な書き方)
- 今年も一年、大変お世話になりました。
- 本年もご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。
- 一年間お付き合いいただき、ありがとうございました。
フォーマル
- 拝啓 師走の候、貴社益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
- 拝啓 年の瀬も押し詰まり、貴社におかれましては益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
- 拝啓 歳末の候、貴社には一層のご発展をお祈り申し上げます。
関連記事
- ビジネスメール・使えるフレーズ集「冒頭の挨拶・書き出し」
お客様へ送る年末挨拶メール向け・感謝の気持ちを伝えるフレーズ
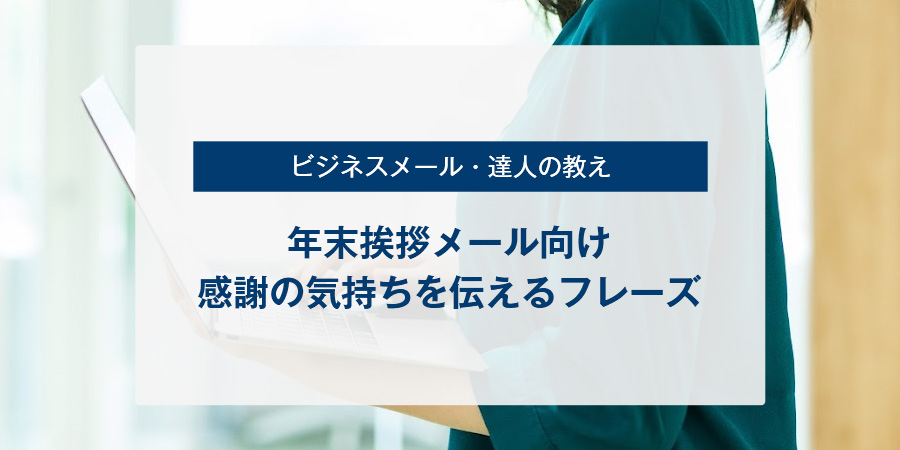
- 本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
- 皆様のお力添えのおかげで、無事に一年を過ごすことができました。
- おかげさまで本年も無事に業務を進めることができました。深く感謝申し上げます。
- ひとかたならぬご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
- 本年も皆様のご支援により、充実した一年を過ごすことができました。誠にありがとうございました。
お客様へ送る年末挨拶メールのトーンと表現の選び方

メールのトーンは、お客様との関係性に応じて調整します。
「拝啓 師走の候、貴社益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます」のような挨拶は、ビジネスメールでは非常に珍しい表現です。しかし、「会社として正式な文章として出している」という場合や大手企業では利用することもあります。
一般的には、個別のお客さまに対しては上の文例の【カジュアル】(一般的な書き方)をつかってください。
お客様へ送る年末のご挨拶メール向け・サンプル
年末のご挨拶と御礼
田中次郎様
お世話になっております。
一般社団法人日本ビジネスメール協会の山田太郎です。
今年はお仕事の場において
ご縁をいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、お力添えを賜りながら
無事に年末を迎えられること、心より感謝しております。
来年も、引き続きご期待に添えるよう努力してまいる所存です。
どうぞ変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、
穏やかなお年を迎えられますことをお祈り申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会
総務部 山田 太郎(YAMADA Taro)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 KIMURA BUILDING 5階
電話 03-5577-3210 / メール [email protected]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会 https://businessmail.or.jp/
アイ・コミュニケーション公式サイト https://www.sc-p.jp/
ビジネスメールの教科書 https://business-mail.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末のご挨拶とご報告
田中次郎様
お世話になっております。
一般社団法人日本ビジネスメール協会の山田太郎です。
今年も残りわずかとなりましたが、
本年は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで、田中様のご支援のもと、
多くの場面で貴重なご意見やご指導をいただき、
大変有意義な一年を過ごすことができました。
来年もさらに飛躍し、ご期待に応えるべく精進してまいりますので、
引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
どうぞご健勝にて良き新年をお迎えくださいませ。
来年もお目にかかれることを楽しみにしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会
総務部 山田 太郎(YAMADA Taro)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 KIMURA BUILDING 5階
電話 03-5577-3210 / メール [email protected]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会 https://businessmail.or.jp/
アイ・コミュニケーション公式サイト https://www.sc-p.jp/
ビジネスメールの教科書 https://business-mail.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お客様向け年末の挨拶メールで言ってはいけないこと・避けるべき表現とは

不必要なセールス要素
年末の挨拶メールに、過度なセールス色を出すのは避けましょう。ただし、年末にキャンペーンを行っていて、それが期間限定のものならばさりげなく伝えましょう。
期限を越えてキャンペーンの存在を知ったときに、お客さまが不快になるリスクを回避するためです。特典やお知らせなど軽い情報提供は問題ありませんが、あくまでも年末の挨拶が主目的だと考えましょう。
否定的な言葉を避ける
感謝の気持ちを伝え、気持ちよく年を越してもらうため為に送るメールです。そのため、ネガティブな表現は使わずに、ポジティブな表現に努めるべきです。
感謝の気持ちを中心に、今後の明るい見通しを述べましょう。
お客様へ送るメールで誤字脱字や送信ミスを防ぐための対策

年末挨拶メールは、同じ内容で多くのお客様に送ることが多いため、誤字脱字や送信ミスには特に注意が必要です。
全員分を送信し終わった後に、誤字があった場合非常に残念な気持ちになるでしょう。小さな誤字の場合は、再送する必要はありませんが、誤解を与えたり、意味が伝わらないような大きな誤字の場合は、再送も検討しましょう。
社名やお客様の名前を間違えるのは大きな問題です。文中での呼びかけは控えるか、システムを使って一気に送るなどした方が良いでしょう。
過去のメールを検索して送る対象を選定する場合などは、一人一人名前をコピペして送りましょう。
年末の挨拶メールに返信は届くもの?
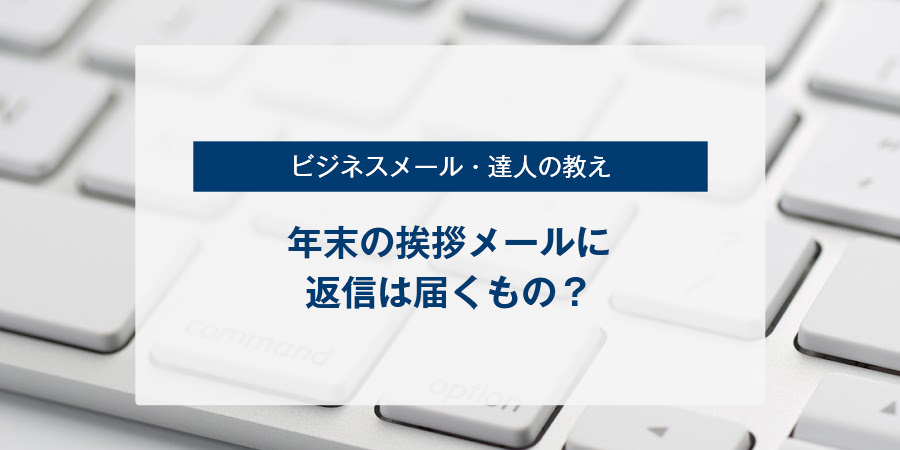
年末挨拶メールに対しては、基本的にお客様から返信を期待する必要はありません。一方的に感謝の気持ちを伝えることが目的となります。
ただし、もし返信が届いたならば、相手に負担をかけない範囲でこちらからも返信をするのが良いでしょう。
The post お客様へ送る年末の挨拶メールの書き方と例文集 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post ビジネスメールは1通に複数の用件をまとめるべきか appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
ビジネスメールを書く際、「1つのメールに複数の用件をまとめるべきか」という質問は、よく挙がるテーマの一つです。
特に、多忙なビジネスパーソンにとって、メールの処理は効率的に行いたいもの。そのため、できるだけ1通のメールで複数の依頼や確認事項を伝えようと考える方も少なくありません。
しかし、重要なのは相手がどのようにメールを処理しやすいかという視点です。メールを受け取る側が混乱せず、スムーズに対応できる形で送ることが、ビジネスコミュニケーションの基本です。
この記事では、1つのメールに複数の用件を含めるべきかどうか、具体的な事例を交えながら解説していきます。
1.ビジネスメールは相手の処理のしやすさを優先する

ビジネスメールにおいて、重要なのは「相手がメールを処理しやすいかどうか」です。
例えば、あなたが外部のデザイナーに複数のプロジェクトに関する用件を一度に伝えようと考えたとします。その際、以下のようなメールを送った場合を考えてみてください。
B、C、D案件に関するご依頼
1. B案件の見積もり依頼
2. C案件のデザイン修正依頼
3. D案件の打ち合わせ日時の調整
このような複数の用件を1通にまとめると、相手はそれぞれの対応にかかる時間が異なるため、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 簡単な用件だけ返信し、残りを忘れる
- すべての用件が終わるまで返信が遅れる
たとえば、B案件の見積もりはすぐに対応できるとしても、C案件のデザイン修正には時間がかかるかもしれません。
その場合、相手は「すべての依頼に対応してから返信しよう」と考え、結果的に全体の返信が遅れるリスクが高まります。このような状況を避けるためにも、異なる種類の用件はメールを分けて送る方が無難です。
2. 同じジャンルの軽い依頼なら一通のメールにまとめても良い

一方で、複数の用件を1通のメールにまとめても問題ないケースもあります。それは、用件のジャンルが同じで、かつ軽い内容の場合です。
例えば、以下のような内容なら1通のメールにまとめても支障はないでしょう。
B、C、D案件の面談調整
1. B案件の見積もりに関するオンライン面談の調整
2. C案件のデザイン修正に関する面談の調整
3. D案件の打ち合わせ日時の調整
この例では、いずれも「オンライン面談の日程調整」という同じ種類の依頼です。相手はカレンダーを見ながら、まとめて日程を調整することができ、対応の一貫性があるため混乱を招くことがありません。
このように、同じジャンルで軽めの依頼や調整であれば、1通のメールにまとめても相手に負担をかけず、スムーズな処理が可能です。
3. 報告メールの場合はどうする?

報告業務においても、1通にまとめるか分けるかは相手の処理のしやすさで決めるのが基本です。たとえば、社内での定期的な日報や進捗報告など、比較的軽く処理できるものは1通にまとめても問題ありません。
しかし、重要な案件の報告や、相手がしっかりと確認する必要がある内容であれば、それぞれの報告を分けた方がよいでしょう。
たとえば、複数のプロジェクトに関する進捗報告や、異なる部門への報告書などは、それぞれのプロジェクトや部門ごとに分けて送信する方が、相手にとっても処理がしやすく、内容を確実に把握してもらえます。
また、報告内容が異なる場合、「予告」を入れることで相手に意識させる方法も効果的です。
例えば、B案件の進捗報告を1通目で送った後に、「このあと、C案件のデザインについても別途メールで報告いたします」と記載することで、相手に後続のメールを認識させることができます。
こうした予告を活用することで、複数の報告内容を効果的に伝えることが可能です。
4. メールを分けた方が無難な場合

メールを1通にまとめるか、複数に分けるかで迷う場面はよくあります。しかし、用件の種類が異なる場合や、重い内容が含まれる場合は、分けた方が無難です。
例えば、見積もりの依頼、デザインの修正、打ち合わせの日程調整など、全てを一度に伝えたいと考えるかもしれませんが、これらは対応のスピードが異なる可能性が高く、相手にとって負担になる場合があります。
一方で、メールの本数が増えることを心配する場合もあるでしょう。そのようなときは、予告を入れることや、軽い用件をまとめるなど、相手がメールを見逃さない工夫をすることで、メールの本数が増えても相手の負担を軽減できます。
基本的には、「まとめるか分けるかで迷うなら、分ける方が無難」という考え方が安全です。特に、時間のかかる依頼や確認が必要な内容であれば、個別にメールを送ることで、相手も自分のペースで対応がしやすくなります。
まとめ
ビジネスメールに複数の用件を含めるべきかどうかは、相手がどのように処理しやすいかが重要な判断基準です。同じジャンルの軽い用件であれば1通にまとめても問題はありませんが、ジャンルが異なる場合や、重い内容が含まれる場合は、分けて送ることが推奨されます。
また、報告メールにおいても、重要な内容は分けて送ることが相手にとって親切です。
最終的には、メールの本数を減らすことを優先するよりも、相手がスムーズに対応できるように配慮することがビジネスコミュニケーションの鍵となります。
複数のメールを送る場合は、予告を活用するなどして、相手の負担を軽減しながら、確実に伝わるメールを心がけましょう。
The post ビジネスメールは1通に複数の用件をまとめるべきか appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post 印象の良いビジネスメールを書くために語彙力を高める必要はある? appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
ビジネスシーンでは、正確かつ効果的にコミュニケーションを図るために「語彙力」が重要だとよく言われます。しかし、「語彙力を高める」と聞いた時、ただ多くの言葉を知っていることを指すわけではありません。むしろ、その言葉を適切に使いこなす力が求められます。
特にメールなどの文章では、相手の理解を優先することが重要であり、難しい言葉を使っても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。
本記事では、ビジネスメールにおける語彙力の本質と、その役割について詳しく解説していきます。
ビジネスにおける語彙力は「使いこなす力」

語彙力と言うと、多くの言葉を知っていることを想像する人が多いですが、ビジネスシーンで求められる語彙力は単に知識を持つことではなく、その言葉をいかに適切に使えるかが鍵となります。
たとえば、同じ言い回しでも状況や相手によって言葉を使い分けることが求められます。
多くの言葉を知っていても、相手が理解できない言葉を使っては意味がありません。特にメールでは、対面でのコミュニケーションと異なり、相手の表情や反応を直接確認できません。言葉が伝わっているかどうかをすぐに判断することができないため、言葉選びには慎重さが必要です。
また、難しい言葉を多用することが必ずしも高い語彙力を示すわけではありません。むしろ、相手がその言葉を知らない場合、コミュニケーションは滞り、ビジネスの効率が低下することもあります。
そのため、ビジネスにおいては、相手が理解しやすい言葉を選んで使いこなすことが、真の語彙力と言えるでしょう。
ビジネスメールに難しい言葉は不要?

「難しい言葉を知っている方がビジネスでは有利ではないか」と考える人もいるでしょう。しかし、ビジネスメールにおいては、難しい言葉を使うことが必ずしも良いとは限りません。メールの受け手がその言葉を理解できなければ、内容が伝わらず、結果的に無意味になってしまいます。
例えば、「不可解」という言葉は理解しやすいですが、「難解」という言葉に置き換えた途端、少しわかりづらくなる場合があります。これは、相手の語彙力や背景に左右される部分もあるため、相手の知識レベルに合わせた言葉選びが重要です。
さらに、ビジネスメールでは「常用漢字」を使うことも推奨されます。たとえば、「叶う」という漢字は、一般的にひらがなで「かなう」と書かれることが多いです。常用漢字でない場合、メールの読み手がスムーズに理解できるように、あえてひらがなを使用することが、相手に配慮した語彙選択の一環です。
ビジネスメールは相手に対して適切な言葉を選び、伝えることが重要

ビジネスメールの中で最も大切なのは、相手に伝わることです。そのためには、相手が理解しやすい平易な表現を使うことが不可欠です。
特に、一般顧客向けのメールやメルマガなどでは、中学校卒業程度で理解できる平易な文章で書くことが求められます。
もちろん、専門的な用語や難しい表現を使うことが必要な場面もありますが、それは主に特定の業界や法人同士のやり取りに限定されます。一般的なビジネスメールでは、できるだけ簡単な言葉を選び、誤解や余計な手間を避けることが効果的です。
たとえば、メールで「確認をお願い申し上げます」という表現よりも「ご確認ください」といったシンプルな表現の方が、読み手にとって理解しやすく、迅速な対応を促すことができます。語彙力とは、多くの難しい言葉を知っていることではなく、適切な言葉を選んで、的確に相手に伝える力を指します。
ビジネスメールで語彙力を高めるためのアプローチとは

語彙力を高める必要はあるのでしょうか?
その答えは、「理解できる語彙を増やすことは重要だが、使う語彙は平易なものにする」という考え方です。ビジネスにおいては、伝わることが最優先されるため、使う語彙はあくまで相手が理解しやすいものを選ぶべきです。
しかし、自分自身の理解力を高めるために、難しい言葉や専門用語を学ぶことは役立ちます。
語彙力を高めるためには、次の2つのアプローチが有効です。
1.伝える語彙をシンプルにする
ビジネスメールでは、相手がスムーズに理解できるよう、平易な言葉を使うことが最も効果的です。相手にとって難解な言葉を避け、できるだけ短く簡潔に書くことがポイントです。
2.理解できる語彙を増やす
一方で、自己研鑽のために難しい言葉や専門用語を学ぶことも重要です。これにより、理解力が向上し、相手の業界や特定の分野での会話がスムーズになります。難しい言葉は使わない方が良い場面が多いですが、理解していることはコミュニケーションの裏付けになります。
このように、使う語彙はシンプルに、理解する語彙は増やすという2方向のアプローチが、ビジネスシーンでの語彙力向上に役立ちます。
まとめ
ビジネスにおいて語彙力を高めることは、単に多くの言葉を知ることではありません。重要なのは、相手に伝わりやすい言葉を選び、使いこなすことです。
難しい言葉や専門用語を無理に使うのではなく、相手の理解に基づいて平易な表現を選ぶことが、効果的なコミュニケーションを促進します。
また、語彙力を高めるためには、伝わりやすい言葉を意識的に選びながらも、自分の理解力を高めるために新しい言葉を学ぶことが重要です。
ビジネスメールでは、相手に伝わることが最優先であるため、難解な言葉は避け、シンプルで明確な表現を心がけましょう。このアプローチによって、相手との円滑なコミュニケーションが実現し、より良いビジネス関係を築くことができます。
The post 印象の良いビジネスメールを書くために語彙力を高める必要はある? appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post ビジネスメールは3行で書くべき?専門家が解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
ビジネスシーンにおいて、「メールは短く簡潔に書くべきだ」という意見はよく耳にします。その中でも、特に注目されているのが「3行メール」というスタイルです。
これは、文字通り3行で用件を伝えることを目指したメールの書き方です。ビジネスの効率化を図るために、できるだけ短く、必要な情報だけを伝えることが推奨されることがあります。
しかし、果たしてこの3行メールは本当に合理的なのでしょうか?メールはただの情報伝達手段ではなく、相手とのコミュニケーションを育むツールでもあります。
どんなに短いメールでも、相手に不快感を与えてしまったり、誤解を招いたりすれば、かえって仕事の効率を下げてしまうこともあります。本記事では、3行メールの利点と問題点を整理し、合理性について深掘りしていきます。
ビジネスで使う「3行メール」の合理性とは

「メールをできるだけ短く書くべき」という考え方には、一定の合理性があります。特に忙しいビジネスパーソンにとって、長々としたメールを読む時間を割くことは難しいものです。
3行で簡潔に用件を伝えられれば、相手にとっても負担が少なく、すぐに対応してもらえる可能性が高まります。
例えば、上司や取引先への確認事項や報告を短くまとめることで、受け手もすぐに返信しやすくなります。次のような短いメールであれば、効率的にコミュニケーションが進むでしょう。
会議資料の確認
営業部の皆様、お疲れ様です。
総務部の山田太郎です。
次回の会議資料を添付します。
内容をご確認の上、フィードバックをお願いします。
締め切りは10月20日です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会
総務部 山田 太郎(YAMADA Taro)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 KIMURA BUILDING 5階
電話 03-5577-3210 / メール [email protected]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会 https://businessmail.or.jp/
アイ・コミュニケーション公式サイト https://www.sc-p.jp/
ビジネスメールの教科書 https://business-mail.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このように、ポイントを押さえた3行メールは、無駄な情報を省き、相手がすぐに行動を取れるよう促す効果があります。
特に、日常的にコミュニケーションをとっている相手であれば、3行メールは非常に効果的な手段となり得ます。
関連記事
ビジネスで使う「3行メール」の問題点について

しかし、3行メールにはいくつかの問題点も存在します。特に、相手との関係性やメールの内容に応じて、短すぎるメールが逆効果になることがあるのです。
例えば、以下のような状況を考えてみましょう。
相手が3行メールに不快感を抱く可能性がある
3行で用件を済ませると、相手に対して冷たく感じられたり、無礼に思われることがあります。特に、初対面の相手やフォーマルな関係においては、簡潔すぎるメールが不適切とされる場合があります。
関連記事
誤解や行き違いが生じやすい
短すぎるメールは、詳細な説明を省いてしまうため、相手に誤解を与えるリスクがあります。例えば、「了解しました」という一言だけの返信が、相手によっては不満や無関心と捉えられることもあるのです。
他の社員や第三者に誤解を与える可能性がある
さらに問題なのは、3行メールを見た他の社員や部下が、それを標準的なコミュニケーションスタイルと誤解してしまうケースです。
例えば、ある上司が部下に対して3行メールを送った場合、そのメールが他のメンバーに転送されると、「3行で返信すれば良いのだ」と学習してしまい、状況に合わない短いメールが送られる恐れがあります。
ビジネスで「3行メール」を使うべき場面とは?

では、どのような場面で3行メールを使用すべきなのでしょうか?それは、相手が短いメールで対応できると判断できる場合や、日常的なやり取りで信頼関係が築かれている場合です。
たとえば、定期的な報告や進捗確認など、繰り返し発生するシンプルな業務では、3行メールは十分に機能します。
次のようなケースでは、3行メールが適していると言えます。
| 場面 | 3行メール例 |
|---|---|
| 定期的な進捗報告 | プロジェクトの進捗は順調です。次回の報告は10月20日に予定しています。 |
| 簡単な確認事項 | お打ち合わせの日時は、10月22日でよろしいでしょうか? |
| 軽い挨拶とお礼 | 昨日はご対応いただき、ありがとうございました。次回のご依頼もよろしくお願いいたします。 |
このような日常的なやり取りや定型的な報告であれば、3行メールは相手に負担をかけず、スムーズに処理してもらえるでしょう。
しかし、それ以外の場面では、慎重に使用する必要があります。
ビジネスで「3行メール」を避けるべき場面とは?

一方で、重要なビジネスシーンや、相手との関係性が築けていない場合には、3行メールは避けるべきです。
特に、取引先やクライアントに対しては、詳細な説明や誠意を込めた挨拶が求められることが多いため、短すぎるメールは逆効果となる可能性が高いです。
次のような場合には、3行メールを避け、丁寧で具体的な内容を心がけましょう。
初めての取引相手への提案
初めての取引相手への提案の場合、詳細な説明や背景をしっかりと伝えることが必要です。短いメールでは、信頼感を得ることが難しくなります。
クレーム対応やトラブル報告
クレーム対応やトラブル報告の場面では、相手の不満や疑問に対して十分な説明を行い、真摯な対応を示すことが重要です。3行メールでは、相手に誠意が伝わらない可能性があります。
関連記事
フォーマルな連絡
ビジネス上の正式な案内や報告は、形式を守ったメールが求められます。3行メールでは、相手に対して軽んじている印象を与えるリスクがあります。
まとめ
「3行メールは本当に合理的なのか?」という問いに対しての答えは、ケースバイケースです。確かに、3行メールは短時間で読めるため、忙しいビジネスパーソンには非常に合理的な手法といえます。
しかし、それは相手との関係や内容によって使い分けるべきです。信頼関係が築かれている場合や、軽い用件であれば3行メールは効果的ですが、重要な連絡や初対面の相手には、より丁寧で具体的なメールが求められます。
メールは単なる情報伝達の手段ではなく、コミュニケーションを深めるツールでもあります。相手に不快感を与えず、誤解を招かないためには、状況に応じた適切なメールの書き方を心がけることが重要です。
3行メールに頼りすぎず、相手の立場に立った柔軟なコミュニケーションを行うことで、ビジネスの信頼関係を築いていきましょう。
The post ビジネスメールは3行で書くべき?専門家が解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post 就職活動に使える!メールアドレスの基本・作り方・活用法 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>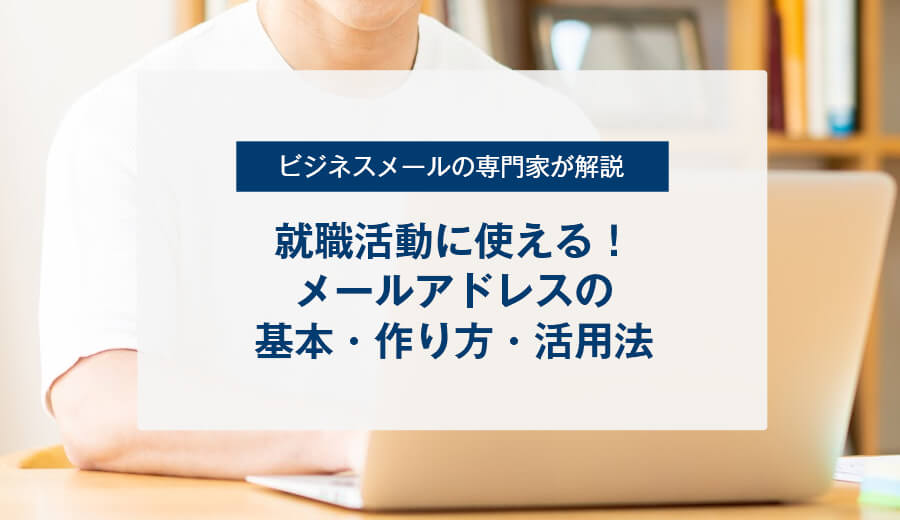
就活サイトへの登録、志望企業へのエントリーやOB・OG訪問など、就職活動をする上でメールは欠かせないツールです。多くの人がスマートフォンを持つ今、一つくらいはメールアドレスを持っていると思います。とはいえ、プライベートで使用しているメールアドレスをそのまま就職活動で使用してもよいのか、悩む学生もいるのではないでしょうか。
たかがメールアドレスと侮ってはいけません。使用しているメールアドレスや活用法が、企業側から見た自身の印象を良くも悪くも変える可能性があるのです。就職活動は、社会人生活へ向けての第一歩。輝かしい未来を迎えるためにも、選ぶべきメールアドレスのポイントを押さえておきましょう。
就活で使うメールアドレスはパソコンでの使用を前提に作りましょう

就職活動を始める際には、プライベートで使用しているアドレスとは別のアドレスを準備しておくと便利です。Gmailのようなフリーメールでもいいですし、大学から発行されているアドレスがあればそれでも構いません。いずれにしても、スマートフォンではなくパソコンでの使用を前提としたアドレスを取得しておくことがおすすめです。
多くの社会人は、仕事用のアドレスとプライベートのアドレスを分けています。サラリーマンであれば、単に「勤務先からアドレスが与えられるから」ということもありますが、起業家やフリーランスの場合でも、仕事用とプライベートのアドレスは分けていることが大半。両者の間に線を引く意味合いもありますが、何より管理しやすいことが大きな要因です。
就活サイトへ登録していると、日々、多くのメールが届きます。複数のサイトへ登録しているともなればなおさら。就職活動を進める中で、志望する企業からの連絡など、大切なメールを見落としてしまうようなことだけは避けたいですよね。就職活動とは関係のないプライベートな情報も混在してしまっては、見落とすリスクは高まるばかり。必要な情報だけを一か所に集約することで、管理しやすい環境を整えることができます。
メールの機能面にも注意が必要です。就職活動中は、企業からのメールに資料や書類が添付されていたり、こちらから応募書類を送ったりする機会もあります。各携帯電話事業者から提供されるキャリアメールでは送受信できるデータ容量の上限が小さいこともあり、思うように書類の受け渡しができないといった事態が発生してしまうかもしれません。
就職活動でビジネスメールのスキルを磨く

何より忘れてほしくないのは、就職活動は、社会人生活へ向けた第一歩だということです。内定を受けることがゴールに見えるかもしれませんが、それは同時に、新たなステージの幕開けを意味します。社会人になれば、就職活動中よりもメールでコミュニケーションを取る機会が増えるかもしれないことは、十分に予想できますよね。
2024年6月に一般社団法人日本ビジネスメール協会が発表した「ビジネスメール実態調査2024」によると、メールの送受信に使用している主な機器として99.27%の人がパソコンと回答しています。仕事上のメールのやりとりは、スマートフォンよりもパソコンを使用するケースが主流。それを思えば、就職活動中からパソコンでのメールのやりとりに慣れておくことが効果的といえます。
メールを書く際、スマートフォンでフリック入力をした方が早いという人もいるでしょう。確かに、就職活動中という限られた期間でみれば、その方が効率的かもしれません。しかし、入社後の自分がパソコンでメールのやりとりをする姿を想像するならば、早い段階からキーボードを使用してメールを書くことに慣れておきたいもの。結果、それが将来の効率的な業務の進行や、自身のイメージをアップさせることにもつながるのです。
一通のメールを書くのに5分でできる人と10分かかる人がいたとして、成果が変わらないならば、5分で書ける方がいいですよね。また、企業に所属すれば、上司や先輩の前でパソコンを使用するのはもちろん、職種によっては、お客さまの目の前で入力する機会が訪れることもあります。キーボードでの入力がおぼつかなければ、頼りない印象にさえ映ってしまうかもしれません。メールを書くのは、社会人として一生もののスキル。就職活動中は、ビジネスメールのスキルを磨く絶好の期間と考え、ぜひ、取り組んでみてください。
就活で使うメールアドレスは名前を基本にシンプルに

では、実際にGmailなどのフリーメールでアドレスを作成する場合のポイントを押さえておきましょう。
就職活動においては、メールアドレス一つで印象が良くも悪くも変わることがあります。好きなスポーツチームやアーティストなど趣味に由来するアドレスは、プライベート感が強く、印象を下げる可能性があるので避けるべき。
就職活動で使用するアドレスは、自身の名前をベースに作成するのが基本です。ただし、フリーメールでは、名前に関するアドレスはすでに取得されていて利用できないケースも少なくありません。その場合は、学籍番号などの数字を組み合わせてアレンジするのが無難。自身の名前が利用できないからといって、ニックネームなどで設定することも避けましょう。
- misaki-miyamoto@~
- m-miyamoto1029@~
関連記事
送信者名の設定で就職活動の第一印象もアップ
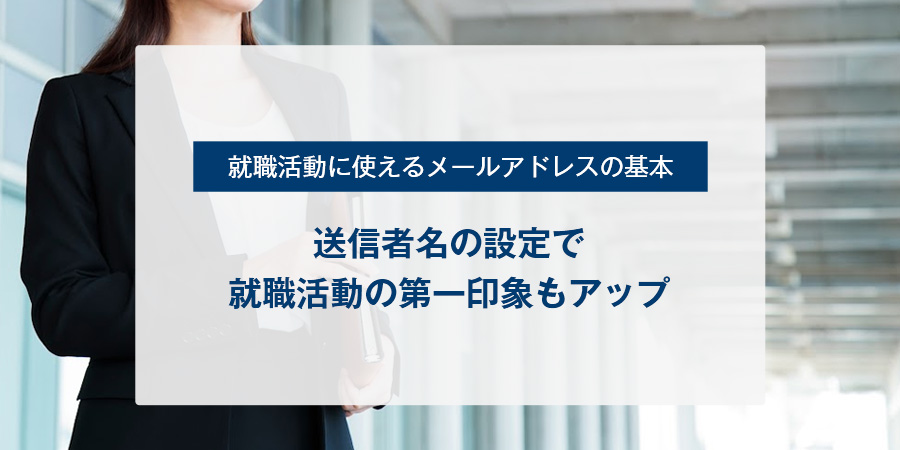
メールアドレスを取得したら、併せて実施しておきたいのが送信者名の設定です。送信者名とは、自分がメールを送ったときに相手の受信トレイに表示される名前のこと。適切な送信者名を設定することが、就職活動でメールを使う上での信頼獲得につながるのです。
就職活動中は、企業の採用担当者と直接やりとりをすることになります。その際、面識のない相手であることがほとんどのはず。メールの送信者に心当たりがなければ、相手にも少なからず警戒心が生まれます。「誰だろう?」と考えながら開封するメールよりは、開く前に誰なのかが分かるメールの方が好印象につながりますよね。
次の三つの表示名を比較してみてください。就職活動中の学生からのメールだと一目で判断できるのはどれでしょうか。
- Misaki Miyamoto
- 宮本美咲
- 宮本美咲(〇〇大学)
言うまでもなく(3)の表示名ですよね。送信者名は、メールソフトのアカウント設定で自由に編集ができます。自身のフルネームと大学名が表示されるよう設定しておけば、面識のない相手であっても安心してメールを開くことができるはず。この機能を活用しない手はありません。
関連記事
企業の担当者は、複数の学生からのメールを受信しています。さらに、学生に限らず社内のスタッフや取引先など多くの方とやりとりをしていることでしょう。誰からのメールなのかが一目で分かることが、相手への配慮につながり、円滑なコミュニケーションも期待できるのです。
使用するメールアドレスや活用法によって、自身の印象は左右されるもの。就職活動におけるメールのポイントを押さえ、社会人生活に向けた第一歩を踏み出しましょう。
The post 就職活動に使える!メールアドレスの基本・作り方・活用法 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post 就活メール返信の基本!返信一つで印象が変わる appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
就職活動を進める中で、企業からメールで連絡を受ける機会もあります。面接対策をしっかりと行っている学生でも、メールの返信には悩むことが多いようです。
- メールは必ず返信したほうがいいの?
- 「承知しました」だけでメールを返信しても大丈夫?
- メールの返信はいつまでにすればいいの?
本記事では、就職活動を進めていく上で欠かせない「メールの返信」に関する疑問を解消します。
就活メールは双方向のコミュニケーションツール

企業の担当者から個別にメールで連絡を受けた場合は、必ず返信をしましょう。当たり前のことと感じるかもしれませんが、できていない学生がいるのも事実。
例えば、企業側から会社説明会や面接の日程について連絡を受けた際、そのメールに返信することなく、当日、会場に姿を見せる学生も珍しくはありません。
指定された日時、約束の日時に相手のもとを訪れたからといって、十分な信頼関係を築くことはできるでしょうか。
メールは、双方向のコミュニケーションツールです。大学のキャンパスにある掲示板のように、一方向の情報伝達手段ではないことを理解しておく必要があります。
メールを使用したコミュニケーションは、自分と相手との互いの意思が伝わりあってこそ成立するもの。企業側から会社説明会や面接の日程について連絡があったならば、訪問する意思が相手に伝わって初めて、コミュニケーションは成立したといえるのです。
当たり前のことができなければ、次のステップへと進むチャンスは遠のくばかり。「名前を呼ばれたら返事をする」のと同じように「メールを受信したら返信する」を習慣化させましょう。
関連記事
就活メールを返信するときは会話よりも具体的に伝えましょう

企業側からの連絡に了承した旨だけを伝えたい。これだけでもメールの書き方に悩むという声を聞きます。次回の面接日程が確定したという連絡に対して、次のような返信だけで十分なのかが不安だというのです。
- 承知いたしました。
- ありがとうございます。
相手に伝えたいのは、面接の日程を理解したことと感謝の気持ち。もし、対面でのやりとりであれば、これだけでも会話として成立するかもしれませんね。
しかし、メールでは淡泊な印象に見えてしまうことも事実。とかく対面による会話では、主語など言葉の一部が省略される傾向が見られます。互いに意思の疎通が図れていることを、相手の反応や表情からうかがうことができるからなのかもしれません。
しかし、メールはその場では相手の反応が分からないツール。言葉を省略せずに、具体的に伝えることがポイントです。
面接の日程について
エグザンプル株式会社
総務人事部
田中様
お世話になっております。
○○大学○○学部○○学科の鈴木翔太です。
次回の面接予定について、ご連絡いただきありがとうございます。
○月○日(○)○時に貴社へ伺います。
当日、持参する書類についても承知いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
──────────────────────
鈴木 翔太(スズキ ショウタ)
○○大学 ○○学部 ○○学科
〒123-4567
東京都○○区○○一丁目2-3
携帯電話:080-****-****
メール:s-suzuki@******.com
──────────────────────
上記の例文は、連絡をいただいたことへのお礼を述べています。その他、面接の日程を調整してくれたことへの感謝を伝えるのもよいでしょう。とにかく、感謝の対象を具体的に書くことが大切です。
面接の日時を具体的に復唱すれば、互いの認識が一致していることの裏付けにもなります。当日の持ち物など付随した情報も伝えられたとしたら、漏れなく触れることが相手の安心にもつながることでしょう。
就活メールの返信は相手に適したタイミングと時間帯を意識しましょう

メールの返信は早いに越したことはありません。とはいえ、複数の企業にアプローチしたり、大学の授業に出席したりしていると、一日中メールをチェックするのは難しいですよね。
「メールの返信は24時間以内に」
こうした目安を耳にしたことがあるかもしれません。就職活動中の心得のように書かれていることも多いですが、その解釈については注意が必要です。ここでいう24時間以内は、あくまでもリミット。それ以上に意識しておきたい目安が存在します。それは、当日中、もしくは翌朝までには返信をするということです。
就活メールの返信は当日中、もしくは翌朝までには送信しましょう
企業の採用担当者であれば、仕事で日常的にメールを使用していることが想像できます。日常的にメールを使用している人であれば、出社時や退勤前のタイミングでメールを確認する可能性が高いでしょう。そこで学生からの返信が確認できれば、きっと安心へとつながるはずです。
前日に連絡したメールに対して、翌朝になっても反応が得られなかったとしたら「メールは読んでもらえただろうか」と不安を覚えても不思議ではありません。
相手に不安を与えないためにも効果的なのが、当日中、または翌朝までの返信なのです。
関連記事
ただし、返信する時間帯にも注意は必要です。テレワークの普及によって、自宅でもメールを確認できる人は少なくありません。
夜遅い時間の返信は相手のプライベートな時間に踏み入ることにもなりかねず、不快感をもたらすこともあります。深夜の時間帯ともなれば、不規則な生活をしている学生だとマイナスの印象を与えてしまうかもしれません。
メールソフトには、予約送信の機能を持つものもあります。そうした機能も上手に活用しながら、相手の就業時間を目安に返信することも心がけましょう。
学生生活の中で、メールをチェックする機会はそれほどないと思います。友人や家族との連絡も、LINEなどのSNSを活用するケースが多いはず。
ただし、就職活動をする中でメールの存在は軽視できません。
手始めに、朝と夕方の一日2回はメールを確認する習慣を身に付けてはいかがでしょうか。それだけでも当日中、遅くても翌朝までの返信は実現できるのです。
就活メールの返信が遅れるとライバルに差がつく可能性も
ライバルに遅れを取らないためにも、受け取ったメールには必ず返信しましょう。面接の日程調整ともなれば、複数の学生に候補日程が提示されているとも考えられます。
自身の希望した日時に他の学生の先約が入ってしまえば、再度、日程の調整を行う必要が生じ、同じ用件で何度もやりとりが繰り返されることに。
早いメールの返信は、それだけ自身の希望と結びつく可能性を高めてくれるメリットもあります。
なにより、企業の担当者に「コミュニケーションが円滑に進む人」という印象を持ってもらえるかもしれませんよね。返信一つで相手に与える印象は変わるのです。
The post 就活メール返信の基本!返信一つで印象が変わる appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post ビジネスメールで挨拶は不要?いる or いらないの議論を専門家が解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>
「メールで挨拶はいらない」
「挨拶は非効率だ」
「社内メールの挨拶をやめるのは、どうしたらいいか」
このような声が増えたのは、実業家の堀江貴文さんの記事が影響していると思います。
この記事が出たのが2021年4月27日。
その数日後、羽鳥慎一モーニングショー(テレビ朝日)から取材が入りました。
2021年4月30日の放送で「挨拶はするべきか、省いてもいいのか」をテーマに、一般社団法人日本ビジネスメール協会代表理事としての見解を述べました。
コミュニケーションは、相手がどう思うか、感じるかが重要です。相手が「挨拶は不要だ」というなら書かなくても問題はないでしょう。相手が挨拶を必要としているの、不要だと考えているのか、分からないなら、挨拶は書いたほうがいいといえます。
「挨拶が不要だ」という声がある一方、
- 挨拶をしない人がいて、冷たく感じる
- 挨拶がないと唐突に切り出されて違和感がある
- 挨拶は、して当然だと思います
このような意見もあります。
私はメールのプロとして現場に入っているためこの両方の言い分は理解できます。効率を重んじるタイプと礼儀を重んじるタイプ。この2つの考え方が、相容れないところもあります。
ビジネスメールで挨拶は不要?この議論を続ける意味が無い!

ただ、これ以上この議論を続ける意味が無いと思っています。メールを何のために使っているのか。迷ったときは「そもそも」を考えるのがいいのです。
- 仕事の効率を上げるため
- コミュニケーションをとるため
- 円滑に仕事を進めるため
これらの目的に異論は無いでしょう。表面的な効率だけを重視している人は、次のような論点から挨拶を省略したがります。
- キータッチの回数を減らしたい
- 文章を読む時間を減らしたい
正直、挨拶を書くのにかかる時間は、1~2秒程度です。
- 「ose」→「お世話になっております。」
- 「taihe」→「大変お世話になっております。」
- 「otu」→「お疲れ様です。平野です。」
このように辞書登録しておけば入力の時間は減らせます。また、通常の挨拶であれば、読むのに1秒もかからないでしょう。この1~2秒の削減の議論をすることが時間の無駄です。
もちろん、このような長い挨拶は不要です。
「入梅とともに雨が続きますが、貴殿におかれましてはなお一層ご隆盛の由拝察いたしております。」
さすがにこれだと読んでいてイライラする人も多いでしょう。挨拶をカットするより、1秒でも早く読めるように、メールの構成やレイアウト、一文の長さに気を遣うべき。
相手が挨拶を書いているから、自分も書かなくてはいけない。それが非効率だと考える人もいるかもしれません。
それなら、1秒で挨拶を入力でいるようにスキルアップすればいい。
挨拶の有無で議論するのはナンセンスであり、わかりやすい文章を書く方法で議論すべきです。
ビジネスメールで挨拶の省略が認められている企業もある
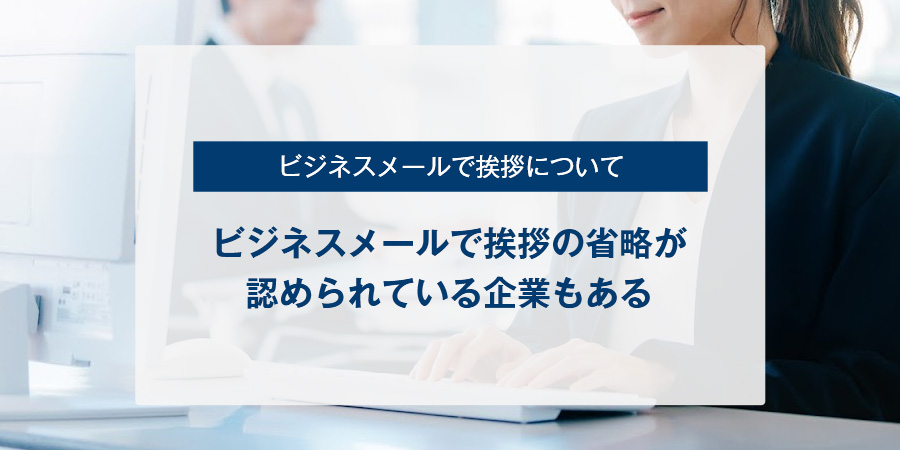
ちなみに、すでに挨拶の省略が根付いている企業もあります。それは、社内コミュニケーションであれば問題ありません。
しかし、社外でも挨拶を省いていいとか、距離が近い人は省いていいとか。誤ったルールを生み出す可能性があります。それにより相手が不快になったとしたら、リカバーにどのくらい時間がかかるでしょう。
先輩のメールを見て崩していいんだと判断した部下が、誤ったメールを外部に送る可能性もあります。
自分のメールが人に見られている。自分のメールが人の見本になる。
こう考えると、挨拶を書くのが合理的だと結論づけられます。そのような意識を持った上で、トータルの時間に目を向けるべき。1通のメールの時間を減らすよりもトータルの業務時間を減らす方法を考えましょう。
The post ビジネスメールで挨拶は不要?いる or いらないの議論を専門家が解説 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post ビジネスメールで受領の連絡が重要である理由 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>今日はちょっと愚痴のような体験談ですが……こう感じている人が多いと思うので共有します。
【なぜ受領の連絡すら出来ないのか】
私(平野友朗)は、日常のコミュニケーションの大半をメールでおこなっています。
例えば、以下のようなやり取りがあります。
- 日程の調整
- 原稿のフィードバック
- サイトデザインの確認
- 原稿の依頼
- 料金の確認
- 講座の内容の確認
などなど。
私の場合、朝出社したら前日に届いたメールは、すべて返信するようにしています。
そして当日の夕方に会社を出るときには、それまで届いたメールを処理します。
仕事の合間に隙間時間がとれれば、そこでもメールの処理をします。
セミナーとセミナーの間でも、5分、10分の時間は捻出できます。
そのような時間があれば、当然メールの処理をします。
そのため、私にメールを送って24時間以内(土日を除く)でメールの返信が無かったら、何かあったと思っていただいて問題ありません。相手の体感とすると、2~4時間以内にはメールの返事が戻ってきているように感じるでしょう。
ごくまれに返事が遅れてしまうことがありますが基本は早いので、催促されることはまずありません。
ビジネスメールで受領の連絡を送るべき理由
メールの返事というのは、回答が揃ってからしなくてはいけないという決まりはありません。
すぐに返事が出来ない場合は「確認をして明日の18時までにご連絡します」と一報入れるだけでOKです。
これによって相手はスケジュールを組みやすいし、臨機応変な対応が可能となります。
この1通のメールがないと、相手は不安になります。
「もしかしたら、届いていないのではないか」
「こちらの意図が伝わっていないのではないか」
そのような心配を無くするためにも、依頼を受けたら「分かりました。金曜日までに作成します」と返信するほうがよいでしょう。
今、私が気になるのは、受領の連絡がやお礼がない人の存在。
たとえば、「メルマガのシステムなのですが、私の場合AとBどちらが良いでしょうか?」のような質問が届くことがあります。基本的に、このような質問に対しても、すべて私が回答を送っています。しかも、しっかり長文で。
その後、
「ありがとうございます。勉強になります」
「早速やってみます」
のようなお礼が届くのが6割くらい。残りは、完全に返事がありません。
何かのサポートセンターに問い合わせをしているつもりなのか、お礼を伝えるという、当たり前のことを知らないのか。このような当たり前の「お礼」が伝えられない人がいることが残念です。
この人は、普段からこんなコミュニケーションをとっているのか……。
もしそうなら、それが癖になっていますし周囲にも「そういう人だ」と認識をされているはず。
おそらく、それが繰り返されると「○○さんの依頼はやりたくないなぁ。」ってなってしまうこともあります。
仕事を有利に進めるためにも、何かをやってもらったら、お礼を伝える。
最低限このくらいのことはすべきですね。
受領のメールに関連した記事
The post ビジネスメールで受領の連絡が重要である理由 appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>The post メールに追われて営業ができない appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>井上賢治講師からの回答
これについては、多くの営業パーソンが同じお悩みを抱えているようです。コミュニケーションツールとしてのメールの特性、そして統計の結果も交えながら考えてみましょう。
メールはいまやビジネスにとって必要不可欠なツールといえます。ビジネスメール実態調査2019においても「仕事で使っている主なコミュニケーション手段」として以下の結果が出ています。
- メール(97.46%)
- 電話(86.91%)
- 会う(66.30%)
私も長らく営業職に就き、飛び込み訪問やテレアポも数えきれないほど行ってきました。しかし、最近では最初の問い合わせがメールという機会も増えました。他の営業パーソンと話をしていても「今日は1日お客さまと会うことがなかった」ということはあっても「メールが1通もない」日はないと聞きます。
「速やか」とはメールを受信した瞬間「今すぐに」とは限らない
さて、ご質問の回答です。上司の方がおっしゃる通り、メールの返信は早いほど相手の方に好印象を与えられます。しかしながらそれは「メールがきたらすぐに」ということではないかもしれません。
例えば、ご自身が営業活動をされている中で、今から30分後のお客さまとの約束に遅れそうになったら、どの手段で連絡するでしょうか。おそらくは電話を選択するのではないでしょうか。緊急性が高く、メールでは送ってもすぐに読まれるとは限らないためです。裏を返せば、メールは緊急度が高い連絡には不向きなツールとも考えられます。
また、先にご紹介したビジネスメール実態調査2019では、返信について、7割を超える人が、1日(24時間)以内に返信がこないと遅いと感じると回答しています。
確かに、多くのお客さまがメールの問い合わせに対して早い回答を求めています。しかしそれは「今日問い合わせたら、今日のうちに回答がくるかな」「遅くても明日には回答がくるだろう」という感覚です。上司の方ともその真意について一度話をしてみてください。「速やかな対応」の「速やか」とはメールを受信した瞬間「今すぐに」とは限りません。
まずは営業訪問の時間をしっかりと確保
解消法としては、1日のスケジュールを立てるうえで、メールを処理する時間を決めることをおすすめします。まずは営業訪問の時間をしっかりと確保しましょう。そのうえで会社にいる時間帯、例えば朝と夕方などにメール対応の時間を決めるのです。それだけでも半日以内の返信は可能です。
ポイントは、メールの返信を先送りにしないことです。お客さまは、回答がないことではなく、リアクションがないことに不安を感じている可能性があります。
例えば、お客さまからお見積りと納期について問い合わせがあったとします。すぐに回答できるのであれば、もちろんすぐに返信をされることでしょう。問題はすぐに回答できない場合です。そんなときでも、まずはリアクションを起こしましょう。
お見積りは提示できるが、納期については製造や物流部門との調整が必要な場合
お見積もりを添付にてお送りいたします。
納期については調整のうえ、本日17時までにあらためてご連絡いたします。
お見積りも納期もすぐには回答できない場合
お問い合わせありがとうございます。
お見積もりと納期につきましては、明日の10時までにご回答申し上げます。
多くの営業パーソンが、問い合わせに対して、すべて回答を揃えたうえで返信しようとします。そうすることで対応に追われ、営業訪問の時間が削られたり、返信が遅れたりという事態に陥ります。先の例文のように、回答できる部分だけ、あるいはメールを確認したことだけでも返信しておくと、お客さまも待たされている感覚がなく、安心感を与えられるはずです。同時にご自身のスケジュール調整もしやすくなるのではないでしょうか。
「メールをスマートフォンに転送」は注意
メールに振り回されない環境を作ることも大切です。近年、営業パーソンにとってスマートフォンは欠かせないツールのひとつとなりました。会社のメールをスマートフォンに転送している方も多く見受けられます。外出先でもメールが確認できる便利さがある一方、その使い方には注意が必要です。
以前の職場で、あるシステム会社との商談のため、上司と同席した際の話です。そのシステム会社の営業は、商談中にもかかわらず、たびたび受信するスマートフォンのメールが気になる様子。視線は私たちとスマートフォンを行ったり来たり。ついには同席していた上司が怒りだし、商談が打ち切りになってしまいました。
私も会社のメールはスマートフォンに転送していますが、受信しても通知されないよう設定しています。通知がなされると、どうしても注意がそちらに向いてしまうからです。本来、集中すべき業務にしっかりと取り組むことが、業務を円滑に進める基本です。これは商談中に限らず、すべての業務において言えることです。
「すぐに回答をしなければならない」という概念を取り払う
一部の特殊な業種を除いて、受信したメールに対して、瞬時に対応しなければならないケースは意外と少ないものです。まずは「すぐに回答をしなければならない」という概念を取り払ってみてください。上司や先輩にもアドバイスを求めながら、半日以内に回答するもの、1営業日以内に回答するものなど、内容によって整理してみるのもよいかもしれません。本来やるべき業務の時間がしっかり確保できるよう、ぜひ実践してみてください。
The post メールに追われて営業ができない appeared first on ビジネスメールの教科書.
]]>